3月、4月は卒業式や入学式シーズン。
人生の節目に、美しい着物姿で臨まれた方も多いのではないでしょうか。
華やかな一日を彩ってくれた大切な着物。
しかし、着用後の適切なケアを怠ると、シミやカビの原因になったり、生地を傷めてしまうこともあります。
そこで今回は、着用後の着物のお手入れ方法から保管方法までを徹底解説いたします。
大切な着物を長く、美しく保つために、ぜひ参考にしてください。
着用後すぐの自分でもできるお手入れ:きれいを保つための基本ケア
楽しい一日を過ごした着物には、目に見えない汚れや湿気が付着している可能性があります。
放置するとシミやカビの原因になるため、早めの応急処置が大切です。
1.風通しの良い場所で陰干しを
まず、帰宅したらすぐに着物をハンガーにかけ、風通しの良い日陰で陰干しをしましょう。
直射日光は色褪せの原因になりますので避けてください。
着物全体に風を通すことで、汗や湿気を飛ばし、カビの発生を抑えることができます。
特に、衿元や袖口、裾など、肌に直接触れる部分は念入りに風を通しましょう。

2.気になる汚れは応急処置を
もし、目に見える汚れを見つけたら、すぐに専門店に相談することが一番ですが、応急処置としてできることもあります。
- 軽い汚れ: 柔らかい布で優しく叩くようにして、汚れを吸い取ります。決して擦らないように注意してください。
- 水性の汚れ: 乾いた布やティッシュペーパーで、水分を吸い取るように優しく押さえます。
- 油性の汚れ: 無理に落とそうとせず、早めに専門店に相談してください。
※ 市販のシミ抜き剤は、生地を傷める可能性があるので、自己判断での使用は避けましょう。
3.帯や小物も忘れずに
着物だけでなく、帯や長襦袢、肌襦袢、足袋などの小物類も、汗や湿気を吸っています。
それぞれ陰干ししたり、風を通したりして、お手入れをしましょう。
特に帯は、型崩れを防ぐために、帯専用のハンガーや平置きで保管することをおすすめします。
本格的なお手入れ:専門店にお任せするのが安心
ご自身での応急処置だけでは落としきれない汚れや、着物全体のクリーニングは、専門の業者に依頼することをおすすめします。
専門店では、着物の状態や用途に応じて、以下のような本格的なメンテナンスが受けられます。
1.丸洗い:着物全体をすっきりリフレッシュ
着物のお手入れで一般的なのが「丸洗い」です。
これは、着物を解かずにそのままドライクリーニングするもので、全体的な汚れを落とすのに効果的です。
着用頻度や汚れ具合にもよりますが、年に1回程度、または目に見える汚れが気になった際に行うと良いでしょう。
ただ、丸洗いでは、汗の汚れは落ちません。
ですので、着用時にとても汗をかいてしまった時は、〝汗抜きクリーニング〟をご依頼ください。
2.部分洗い・しみ抜き:気になる箇所をピンポイントでケア
衿元の皮脂汚れ、袖口の汚れ、食事の際のシミなど、気になる部分的な汚れには、「部分洗い」や「しみ抜き」といった方法があります。
専門の技術を持った職人が、生地や染料に合わせて適切な方法で丁寧に汚れを落としてくれます。
時間が経つと落ちにくくなるシミもあるため、早めに相談することが大切です。

3.ガード加工:汚れや水をはじく頼れる味方
着物を着用する前に「ガード加工」を施しておくと、水や油性の汚れがつきにくくなり、お手入れが格段に楽になります。
特に、雨の日や食事の機会が多い場合に安心です。
一度加工しておけば、効果が長持ちするものもあります。新規で購入した着物はもちろん、お手持ちの着物にも加工できますので、検討してみてはいかがでしょうか。
当店ですと、【パールトーン加工】をおすすめしております。
当店では、パールトーン加工を施している商品であれば、着用汚れ、衿・裾・袖口・のシミ抜きが無料です。(京都にあるパールトーン社までの往復送料・梱包代4,400(税込)のご負担があります。
正しい保管方法:美しさを保ち、劣化を防ぐ
お手入れが終わった着物は、適切な方法で保管することが、長く美しく保つための重要なポイントです。
湿気によるカビ、虫食い、シワの発生など、保管中に起こるトラブルは意外と多いもの。
これらを防ぐためには、「湿気対策」や「虫干し」、「収納方法」や「防虫剤の使い方」など、いくつかの基本を押さえておく必要があります。以下で、正しい保管方法、保管のポイントをご紹介します。
1.湿気対策:カビを防ぐための基本
着物の大敵は湿気です。
湿気の多い場所に保管すると、カビが発生しやすく、生地を傷める原因になります。
そこで、湿気から着物を守るために、保管時にぜひ取り入れていただきたい湿気対策アイテムがいくつかあります。
- 桐箪笥
桐は調湿効果に優れており、着物の保管に最適です。 - 防湿剤・乾燥剤
箪笥や衣装ケースに入れることで、湿気を吸収してくれます。
ただし、種類によっては成分が着物に影響を与える可能性もあるため、和装用のものを選ぶようにしましょう。
定期的な交換も忘れずに行ってください。 - 除湿シート
箪笥や衣装ケースの底に敷くことで、湿気を吸い取ってくれます。
天日に干して乾燥させることで、繰り返し使用できるものもあります。※私のおすすめ!!
トリマス 除湿・脱臭シート タンスの引き出しに一枚広げて被せておけばOK。
私も愛用しています。

2.虫干し:年に数回の風通しで虫食いを防ぐ
年に数回、天気の良い乾燥した日に、着物を虫干しすることをおすすめします。
虫干しは、着物に風を通して湿気を飛ばし、虫食いを防ぐ効果があります。
具体的には、以下の点に注意して虫干しを行いましょう。
- 時期
晴れた日の午前10時から午後3時頃までが目安です。年に2回(梅雨明けの晴れた日と、秋の乾燥した日)行うと良いでしょう。 - 場所
直射日光の当たらない、風通しの良い日陰を選びます。 - 方法
着物をハンガーにかけ、間隔を空けて風を通します。長襦袢や帯、小物類も同様に陰干ししましょう。
3.畳んで収納:シワを防ぎ、美しさを保つ
着物は、丁寧に畳んで保管することが基本です。
・畳み方: 着物の種類によって畳み方が異なりますが、基本的にはシワにならないように、丁寧に畳みます。
不安な場合は、当店にお持ちください。お教えします!!
・たとう紙: 畳んだ着物は、たとう紙(和紙でできた包み紙)に一枚ずつ入れます。
たとう紙は、湿気や汚れから着物を守る役割があります。定期的に新しいものに交換することをおすすめします。

・ 保管場所: 畳んだ着物を重ねて保管する場合は、重いものを上に置かないように注意しましょう。畳みシワがキツくついてしまいます。
4.防虫剤:大切な着物を虫から守る
大切な着物を虫食いから守るために、防虫剤を使用するのも有効な手段です。
- 種類: ナフタリン、しょうのう、ピレスロイド系のものなどがあります。
異なる種類の防虫剤を一緒に使用すると、化学反応を起こして変色の原因になることがあるため、必ず単独で使用しましょう。 - 設置場所: 防虫剤は、箪笥や衣装ケースの隅に置くのが一般的です。
直接着物に触れないように注意してください。 - 交換時期: 防虫剤には使用期限がありますので、定期的に交換しましょう。
入れすぎには、注意です。
基本、正絹(しょうけん)絹のお着物には、虫はつきません。
同じタンスに、ウールのお着物などが一緒に入っていて、そこについた虫がイタズラする場合がありますが。
しょうのうの匂いはお洗濯しても落ちないので、気をつけてご使用ください。
5.定期的なチェック:異変に早期に気づくために
保管している着物は、年に数回程度、状態を確認することをおすすめします。
- 確認ポイント: シミ、カビ、虫食い、変色などがないかを確認します。
- 早期発見: 異変を早期に発見できれば、被害を最小限に抑えることができます。
もし異常が見られた場合は、早めに専門店に相談しましょう。
まとめ
卒業式や入学式で着用された大切な着物。
今回ご紹介したお手入れ方法と保管方法を実践していただくことで、長く美しい状態を保つことができます。
もし、お手入れ方法や保管方法についてご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
お客様の大切な着物を末永く守るお手伝いをさせていただきます。
KIMONOしゃなり寺﨑

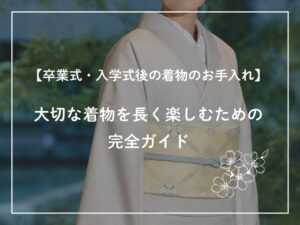


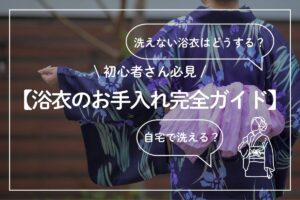


とは?-初心者向け解説-300x225.jpg)

